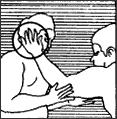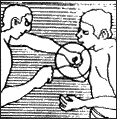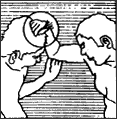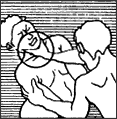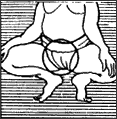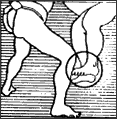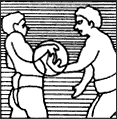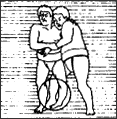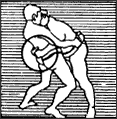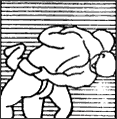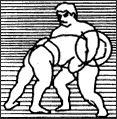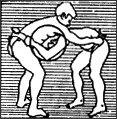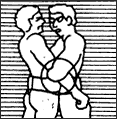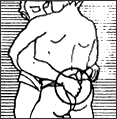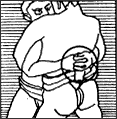ルール説明
対戦方法
午前の部は各小学校毎に集まって相撲の礼儀作法や、取組の練習を行います。
午後の部より各学年別・男女別で個人戦の取組を行います。
1〜3回程度取組を行った後に、勝者は決勝トーナメントへ進出します。
決勝トーナメントではベスト8以上の児童に加点し、個人戦の優勝者を決める他、
個人の加点を集計し、優秀小学校を決定します。
競技心得
相撲は心と体を鍛えることを目的にして行うものです。お互いの攻めと防ぎによって、正々堂々と競技することです。たとえ練習でも真剣に行い、少しでも油断があってはなりません。勝つために競技するのですが、だからといって、やたらと勝ち負けばかりにとらわれると、競技の方法や態度が悪くなって、良くないだけでなく、危険なことにもなるのです。このことを頭の中に入れて、いつも元気よく、自分より大きいからとか、強そうだからとかいってびくびくせず、自分より小さいからといって馬鹿にせず、しっかりした態度で相撲をとることを忘れないようにしなければなりません。
競技前の心得
用便をしておくこと。
食事は少なくとも1時間前にしておくこと。
つめは短く切っておくこと。
準備運動を十分しておくこと。
競技中の心得
元気よく正々堂々と競技すること。
口はしっかりととじて競技すること。
禁じ手を使わないこと。
競技後の心得
礼をして終ること。
体の調子を整えるため、すぐ休まないで、体調運動をすることを忘れないこと。
その他
競技は必ず主審のさしずに従うこと。
呼び出しに応じて二字口で立礼をして競技を行う。
勝負が終わったならば両方とも二字口で礼をし、勝ったものだけがそんきょして主審より勝ち名のりを受けること。
勝ち名のりはそんきょのまま目礼し受けること。
土俵だまりで足を投げ出したり、土俵で足をこすらないこと。
競技に審判員より物言がついたときは、土俵の下におり、主審の指示により行動すること。
競技規定
(わんぱく相撲のために特に定めており、禁じ手等は、いわゆる大相撲とは異なります。)
(1) 勝ち負けのルール
つぎの場合は負けとする。
相手より先に土俵をでたとき。
相手より先に、足のうらよりほかのからだの一部が砂についたとき。
競技中、競技者が腰より上に持ち上げられて危険と認められたとき。
禁じ手を使ったとき。3)を参照。
主審の指示に従わなかったとき。
(2) 立合い
立合いは主審の指示に従い、両手をついて「はっけよい」で立つこと。
「待った」はない。
(3) 禁じ手
これを使うと反則(直ちに中止して審判競技の上 敗けとなる場合と取直しの場合がある)になる。危険を防ぐためのルールであるから、けっして使わないように注意すること。
張り手(平手または拳で殴ること)
拳または指で突くこと
(目、胸等)
髪の毛、のど、前袋をつかむこと
のどをつかむこと
前ぶくろをつかむ
向こうげり
逆指(相手の指を反対側に曲げること)
さば折り
かわずがけ
居ぞり
首抱え込み
頭を相手も胸の真中より下に入り込ませる
後たてみつをつかむこと(結び目はよい)
かんぬき(相手の両腕を外側から締めつけること)
がっしょう(組んでいるとき自分の指を組み合わす)
競技規定
この大会には審判長1名、副審判長若干名、審判員若干名をおいて大会の審判を行う。
審判員は勝負の判定、その他審判に関することに当る
主審の判定に対して副審の間に疑義を生じた場合は、審判長を中心として、主審及び副審判との合議の上決定する。
主審の判定に対して異議の申立ては、担当している審判長並びに副審に限る。
禁じ手を用いた場合は、行儀を中止させ、審判競技のうえ勝負及び取直しを決める。
競技中、負傷によって競技の進行不能と審判が認めたときは、審判合議のうえ負けとすることがある。
競技中前袋の落ちた時は、負けとする。
約3分間の試合で勝負のつかないときは、取直しを行う。
連続2回取直すときは、審判協議のうえ3分以上の休憩を与える。
他の事項については日本相撲連盟大会協議規定に定められた「審判規定」に従うものとし、その運用は大会当日の審判団に委任する。
その他・ここに定めのない事項については実行委員会の決定による。
試合
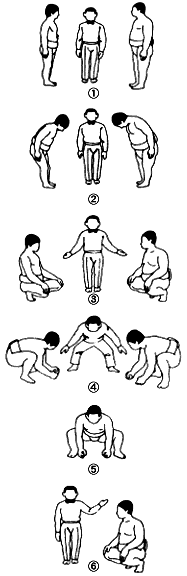 呼出しに応じて二字口でまず立礼して競技を行い、勝負が終わったら両方とも二字口で礼をし、勝った者だけがそんきょして主審より勝名のりを受けること。
呼出しに応じて二字口でまず立礼して競技を行い、勝負が終わったら両方とも二字口で礼をし、勝った者だけがそんきょして主審より勝名のりを受けること。
勝名のりはそんきょの姿勢のまま目礼して受けること。
土俵だまりで足を投げだしたり、土俵で足をこすらないこと。
仕切り
両足を左右に開いて腰を落とし、両手をつくが、ふつう両手の間隔は肩幅ぐらい。もっとも大事なことは、この体勢から相手の目をじっと見ること。それに土俵上では自分勝手にやらないで、おたがいに相手の動作に合わせることも必要。
わんぱく相撲の禁じ手・禁じ技
競技者が禁じ手((1)〜(7))を使った場合、審判はすぐ競技を中止させ、審判員の協議の上、負けとする。禁じ技((8)〜(15))を使った場合、審 判は直ちに競技を中止させ、審判員の競技の上、取り直しとする。取り直し後、再度禁じ技を使った場合、審判員の協議により反則負けとする。ただ し、(14)、(15)については競技中に手を払えば足り、競技を中止させる必要はない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
極まり手
【出し技】
 1.寄り切り
1.寄り切り
もろ差し、右四つ、左四つでもよいから、体をつけて前に出て相手を土倭の外に出すことです。腰を落として、耗手より低くかまえて出ると、よく出られます。
相手がうしろに倒れたとさは、寄り倒しになります。
 2.押し出し
2.押し出し
両手が片手かを相手のわきの下にあてて、押して相手を土俵の外に出すことです。腰を落として出ると、相手はかんたんにさがります。
相手がうしろに倒れたときは、押し倒しになります。

3.突き出し
手のひらが相手の体に直角にあたるように突っ張って、柏手を土俵の外に出すことです。突っ張りには左右をかわるがわる出すのと左右いっしょに出すもろ手突きがあり、どちらも下から上に向って突くと効果的です。
相手を突き倒すと、突き倒しになります。

4.出し投げ
右でも左でもまわしを引き、ひじをわきにつけたまま、相手の体を前に投げ倒すことです。
上手から投げると上手出し投げとなり、下手から投げると下手出し投げとなります。
【投げ技】

1.上手掛げ
四つに組んで、右でも左でも上手まわしを引きつけて投げ倒します。投げを打つときは右上手投げは左足を外側に引いて打つとよくきまります。

2.下手投げ
四つに組んで、右でも左でも下手まわしを引いて投げ倒します。
差して寄り立て、相手が寄り返そうとしたときなどに打つとよくきまります。

3.すくい投げ
四つに組んで、差し手でまわしを引かず相手の体をすくいあげるようにして、投げ倒します。差し手を返し、ひじを上にして投げる必要があります。
 4.小手投げ
4.小手投げ
相手の差し手をかかえ込んで投げます。まわしは引かず、相手の差し手をしっかりかかえて投げるのが有効です。
【倒し技】

1.外掛け
四つに組んでまわしを引きつけて、自分の左足を相手の右足、右足だったら相手の遠足の外側にかけて、うしろに倒します。相手がつりにきたときとか、下手投げにきたときにかけるとよくきまります。

2.内掛け
四つに組んで、自分の左足を相手の右足、右足だったら相手の左足の内側からかけて、うしろに倒します。外掛けと同じように、相手がつりにきたときとか、投げにきたときに掛ける技です。
【特殊な技】

1.つり出し
四つに組んで、柏手のまわしを引き腰を落としてつり上げ、土俵の外に運び出します。つり出すとき、相手の両足が空中にあれば、自分の足が先に出ても「送り足」といって負けになりません。

2.うっちゃり
相手に寄り立てられたとき、土俵ぎわで腰を落として、右または左へ振りすてます。相手が寄って出てくる力を利用した技です。

3.送り出し
チャンスを見て相手のうしろに回り、突くか押すかして相手を土俵の外に出します。
その他の技

1.はたき込み
突っ張り合ったり、押し合っているとき、相手が低く出てくるときに、体を右か左に開いて柏手の肩か背中をはて体を開くとよくきまります。

2.けたぐり
立ち上がったときか、突っ張り合い、押し合い中、左足を飛ばして相手の左足首を、右足を飛ばしたときは相手の右足首をけり、相手の腕を引っ張って前へ落とします。

3.足とり
立ち上がったときか、突っ張り合っているとき、相手の片足を両手でかかえ上げ、自分の体重をかけて倒します。